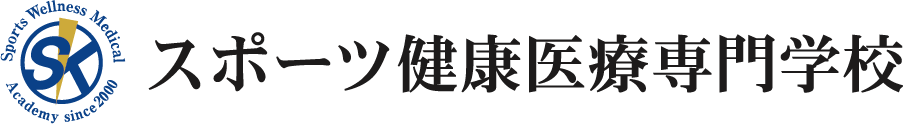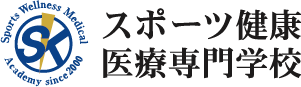「鍼灸師」の読み方と意味:はり師・きゅう師との違いも分かりやすく解説
公開日:2025.06.3

「鍼灸師」という言葉を見かけたとき、どう読むのか、また「はり師」「きゅう師」とは何が違うのか疑問に思う方は多いのではないでしょうか。「鍼灸師」には、読み方や資格の仕組みに独特の特徴があります。
この記事では、「鍼灸師」の正しい読み方や意味、はり師・きゅう師との違い、さらに鍼灸師になるためのステップまで解説します。
鍼灸師の読み方とは?
「鍼灸師」は、漢字で書かれると少し難しく感じるかもしれませんが、「しんきゅうし」と読みます。
スポーツの現場や医療・健康関連のニュース、または美容やリラクゼーションの分野でも「鍼灸師」という言葉を見聞きする機会が増えています。
一方で、「鍼灸師」とは具体的にどんな資格や仕事を指すのか、あまり知られていないかもしれません。実は、「鍼灸師」というのは正式な国家資格の名前ではなく、「はり師」と「きゅう師」という2つの資格を持った人のことをまとめて呼ぶ言い方なのです。
ここでは、まず「鍼灸師」の読み方とその意味、そして「はり師」「きゅう師」との関係について、わかりやすく説明していきます。
鍼灸師(しんきゅうし)という名前の意味
「鍼灸師(しんきゅうし)」とは、「鍼(はり)」と「灸(きゅう)」という2つの伝統的な治療法を専門とする施術者を指す呼び名です。一般的にはこの2つの技術を扱う国家資格者のことをまとめて「鍼灸師」と呼びます。
鍼(はり)は、髪の毛ほどの細さのステンレス製の針を体の特定のツボや筋肉、神経に刺すことで、体内のバランスを整えたり、痛みや不調を和らげたりする治療法です。
灸(きゅう)は、ヨモギの葉から作られる「もぐさ」を皮膚の上に置き、温熱刺激を与えることで効果的な生体反応を利用し、自然治癒力を高める治療法です。
これらの技術は中国に起源を持ち、日本には古くから伝わり、江戸時代には庶民の間でも広く親しまれてきました。現代では、肩こりや腰痛、スポーツ障害、不眠、冷え性、美容、不妊治療など、さまざまな目的で利用されています。
はり師・きゅう師とは
「はり師」「きゅう師」は、それぞれ国家資格の名称です。
| はり師 | 鍼(はり)を用いて、体のツボに刺激を与える治療を行う資格。 |
|---|---|
| きゅう師 | もぐさによる灸(きゅう)を使って、温熱刺激による治療を行う資格。 |
この2つの資格はそれぞれ独立しており、どちらか一方のみを取得して開業することも可能です。ただし、実際には両方の資格を取得し、鍼と灸を併用した施術を行う人が多く、そのような施術者を「鍼灸師」と呼んでいます。
つまり、「鍼灸師」というのは正式な資格名ではなく、「はり師」と「きゅう師」という2つの国家資格の両方を持っている人を指す一般的な呼び方です。一方で、「はり師」と「きゅう師」は、それぞれが国家資格として定められている正式な資格名です。
例えば、肩こりの治療には鍼で筋肉の緊張をほぐし、灸で血行を促すといったように、両技術を組み合わせることでより効果的な施術が可能となります。また、鍼や灸を業として行うには必ず「はり師」「きゅう師」の免許が必要です。無資格での施術は法律で禁止されています。これにより、患者さんは安心して施術を受けられる環境が整っています。
実際の現場では、例えば「スポーツ選手の筋肉疲労には鍼、冷え性には灸」など、症状や体質に合わせて使い分けることが多いです。また、患者さんから「鍼は怖いけど、灸なら受けてみたい」「両方受けてみたい」といったリクエストもあり、柔軟な対応が求められます。
さらに、鍼灸師は医師や柔道整復師、理学療法士、あん摩マッサージ指圧師など他の医療職と連携しながら、患者さんの健康を総合的にサポートしています。最近では、病院やクリニックのリハビリテーション科、スポーツチームのトレーナー、美容鍼灸サロンなど、活躍の場がどんどん広がっています。
鍼灸師の専門用語
鍼灸の世界には、初めて耳にするような専門用語が数多く存在します。これらの用語を知っておくことで、養成校での学びや実際の現場でのコミュニケーションがスムーズになり、より深く鍼灸の世界を理解できるようになるでしょう。
経穴(けいけつ)
いわゆる「ツボ」のこと。東洋医学では、体に約360カ所の経穴があるとされ、症状や目的に応じて使い分けます。
例えば…
- ・合谷(ごうこく) :
頭痛、肩こり、ストレス緩和などに使われる手のツボ - ・足三里(あしさんり):
胃腸の不調、疲労回復、免疫力向上などに効果があるとされる足のツボ
経絡(けいらく)
経穴同士を結ぶエネルギーの通り道。気(エネルギー)や血(けつ・栄養分)が経絡を通じて全身を巡ると考えられ、経絡の流れが滞ると不調が現れるとされています。鍼灸治療は、この経絡の流れを整えることを目的としています。
証(しょう)
東洋医学独特の診断方法。患者さんの体質や症状、脈や舌の状態などを総合的に判断し、最適な治療法を決定します。
西洋医学の「病名診断」とは異なり、東洋医学では「人を診る」ことを重視し、同じ病名でも異なる「証」に基づいた異なる治療が選ばれることがあります。
もぐさ
灸治療で使うヨモギの葉を乾燥・精製したもの。
もぐさの質や形状によって温度や刺激の強さを調整できるため、患者さんの状態に合わせた細やかな治療が可能です。
刺鍼(ししん)
刺鍼とは、鍼(はり)を皮膚に刺す行為およびその技術を指します。鍼の太さや長さ、刺す深さや角度、留置時間などを調整し、個々の症状や体質に合わせた刺激を行います。
患者の安全と快適さを保つためには、確かな技術と豊富な臨床経験が必要です。痛みの少ない刺鍼や、あえて刺激を感じさせる「得気(とっき)」を重視する刺鍼など、さまざまな手法があります。
灸点(きゅうてん)
灸点とは、灸をすえるポイントのこと。多くの場合、経穴と一致しますが、灸治療特有の効果を期待して独自に選定される灸点も存在します。
皮膚の状態や体の反応を見ながら適切な場所を選び、熱刺激の量も調整されます。
その他
鍼灸師は、患者の状態を把握するために東洋医学特有の診察法を用います。代表的なものに以下があります。
- ・脈診(みゃくしん):
手首の動脈の拍動から内臓の状態や体力を判断 - ・舌診(ぜっしん) :
舌の色、形、苔(こけ)の状態から体内のバランスを観察 - ・腹診(ふくしん) :
腹部の圧痛や張り、冷えなどを通じて証を立てる
これらは、養成校で理論と実技の両面から丁寧に学び、実践を通して感覚を養っていく重要なスキルです。
例えば、
「肩こりで来院した患者さんに、経穴の『肩井(けんせい)』や『合谷(ごうこく)』に鍼を打ち、経絡の流れを整える」
「冷え性の方には、足の『三陰交(さんいんこう)』に灸をすえて血行を促進する」
など、専門用語と実際の施術は密接に結びついています。
このように、鍼灸の専門用語を理解することは、施術の幅を広げるだけでなく、患者さんへの説明や信頼関係の構築にも役立ちます。養成校や現場での学びを通じて、少しずつ専門用語に親しんでいくことが大切です。
鍼灸師になるには
鍼灸師になるためには、「はり師」と「きゅう師」の国家資格を取得する必要があります。まずは、高校卒業後に厚生労働省または文部科学省が認可する鍼灸の養成施設(専門学校・短大・大学など)に入学します。ここで、解剖学や生理学、東洋医学の基礎、鍼灸の技術などを学びます。
卒業後、毎年2月に実施される国家試験(筆記)に合格すれば、それぞれの資格を取得できます。合格率は年によって変動がありますが、近年は毎年おおよそ70〜75%程度です。
「はり師」と「きゅう師」の両方の資格を取得することで、一般的に「鍼灸師」として名乗り、医療・福祉・スポーツ・美容など幅広い分野で活躍できるようになります。
まとめ
鍼灸師は「しんきゅうし」と読み、はり師・きゅう師の両方の国家資格を取得することを指します。
はり師・きゅう師の資格を取得することで、鍼灸院の開業や医療・スポーツ分野での活躍が可能となり、将来性も高い職業です。鍼灸の世界に興味がある方は、まずは「鍼灸師」という言葉の意味や資格の仕組みをしっかり理解し、自分の将来像を描いてみてはいかがでしょうか。
「スポーツ健康医療専門学校」の鍼灸科では、鍼灸師に必要な知識や技術を実践的に学ぶことができ、卒業と同時に国家試験の受験資格が得られます。現場を意識した豊富な実習や、国家試験に向けたサポート体制も整っており、即戦力として活躍できる力を身につけることが可能です。
将来的に医療・スポーツ・美容などの分野で鍼灸師として活躍したいと考えている方にとって、こうした専門学校での学びは大きな一歩となるでしょう。
興味がある方は、学校のホームページや資料でスポーツ健康医療専門学校の鍼灸科を確認してみてください。